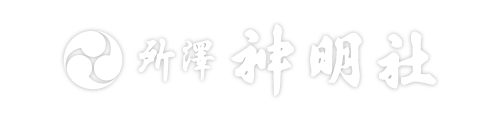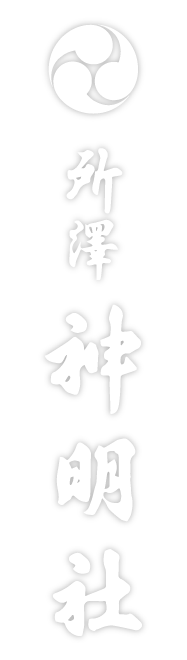秋季例大祭
九月十五日
最も重要なお祭りで、巫女舞の奉納、
神楽殿において竹間澤里神楽が奉納されます。

年間の祭典において最も重要なお祭りです。毎年9月15日に行われます。
祭典後、竹間澤神楽の巫女舞と御神楽が奉納されます。竹間澤神楽とは川越藩の神楽師として活躍していた前田筑前の社中に伝わった神楽です。
式三番で幕をあけ、夜遅くまで芸術性の高い壮麗なお神楽が奉納されます。
 |
 |
 |
| 祭典 | 11:00 |
|---|---|
| 巫女舞の奉納 | 15:00 |
| 御神楽の奉納 | 16:00~20:00頃 |
| 演目 | 住吉三神~寿式三番叟~
天の返し矢 高天原神集:申付 |
 |
 |
 |
秋季例大祭神楽
住吉三神~寿式三番叟~
住吉三神は、前田社中では舞台を清めるため最初に舞われる、約束事の演目です。この演目を舞わずに剣を抜くと怪我をすると言い伝えられています。
伊邪那岐乃命(イザナギノミコト)は亡くなった最愛の妻、伊邪那美乃命(イザナミノミコト)に会うために、黄泉の国まで追ってきました。
そこで、醜い姿に変わり果てたイザナミを見て逃げ出してしまいました。追いかけるイザナミから何とか逃げ延びたイザナギは筑紫にある阿波岐原で禊(みそぎ)をします。
このときに生まれたのが、上筒之男(うわつつのお)命・中筒乃男(なかつつのお)命・底筒乃男(そこつつのお)命の「住吉三神」です。
まず、上筒乃男命による「折り紙」と「剣の舞」が、次に中筒乃男命による「奉納の舞」、底筒乃男命による「扇の舞」が舞われ、舞台の四方が清められます。底筒乃男命は、舞い終わると式三番叟を呼び出します。
式三番叟は、五人囃子と共に賑やかに舞い踊り、住吉三神の演目が終了となります。
天の返し矢
「国譲り」 三部作の一つです。天若日子が大国主のところに国譲りを迫りにや ってくる場面です。天若日子は大国主の命に対し何度となく国を譲り渡すよう 交渉しますが大国主の命は聞き入れません。やがて両者は争いになり、天若日 子は大国主の命に高皇産霊神から授けられた矢を放とうとしますが、大国主の命の 愛娘下照姫(シタテルヒメ)の美しさに一目惚れし、居ついてしまいます。
高天原では、天若日子が数年過ぎても戻ってこないことから不審に思い、雑を使い に出しますが、天若日子はこの雑を矢で射殺してしまいます。矢は雑を射貫き高天原 まで届き、その返し矢が天若日子の胸に突き刺さり、天若日子は大怪我を負ってしま います。
里神楽では、おかめとモドキによる楽しい掛け合いの所作が所々に入れられてお り笑いを誘います。
高天原神集:申付
この演目は、いわゆる国譲りシリーズの三部作のプロローグ (序章)です。 高天原の天照大御神(アマテラスオオミカミ)は、高皇産霊神(タカミムスビノカミ)に、 高天原に反抗を繰り返す大国主 (オオクニヌシ)の命が治めている豊葦原中国(トヨア シハラノナカツクニ)を高天原に差出し、高天原の支配下に入れるよう命じます。 高皇産霊神は、直ちに建御雷神(タケミカズチノカミ)、穂比の神(ホヒノカミ)、天 日子(アメノワカヒコ)を呼び集め、大国主に国譲りをするよう交渉してくることを命じま す。集められた神は、我先に交渉に向かうと血気盛んです。
高皇産霊神は、豊葦原中国に向かう神それぞれに、刀、剣、弓矢をぞれ授けるのです。
 |
 |
 |